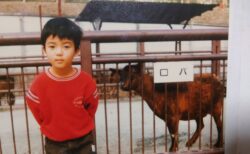いつまでも続くように思われた彩りと灰色の織り交ざった学生生活は、ただの通過点に過ぎなかった。強い現実味を持つ社会に出る前の、ただのモラトリアム期間を過ごしていたのだろうか。それとも、有効性の高い学びを私は得ていたのだろうか。写真はオーケストラ部での練習風景。
株式会社ライクブルーの池田治彦です。
2007年3月、大学の卒業式において当時の学部長が学生たちに、まるで呪いのようなはなむけの言葉を言い放ったことを記憶しています。「”東大法学部卒業”というレッテルは君たちに一生ついてまわる(からそれに相応しい生き方をするように覚悟しておけ、のようなニュアンス)」と。
社会に出てから、その言葉を実感する場面が多かったのも事実です。しかし、私は何度も不思議に思いました。「東京ではたかが4年間過ごしただけで、別にそこで生まれ育ったわけでもなく、人生を決定づけるような特別な何かがあったわけではない。どちらかと言えば、それ以前の約20年間を過ごした生まれ故郷での生活の方が、よほど自分を形づくっていて、真実味のあるアイデンティティ(自己同一性)を持ち得ている。自分自身が誰かを決めるのは大学名ではない」と。
大学卒業後、かりそめのような社会人生活を経て、結果として私は「自分らしさ」を追い求めるように、また福岡の地へ戻りました。その後は「何もかも順風満帆」とは程遠い人生が待っていて、失敗や愚行ばかりで、多くの人に迷惑をかけてきたことは事実です。福岡に戻り、紆余曲折ありながらも約15年の歳月が経った今、もしかすると私は自分らしく生きている実感を得られているかもしれません。
そのリハーサルのようになった大学の4年間は、一生の仲間たちとの出会いにも恵まれつつ、自分のことを嫌に思うこともあり、自らのあり方を決め、己を貫くきっかけとなった場所でもありました。つまり、それがなければ、今の私はありません。それは故郷の時間と同じことであり、人生を構成する掛け算の重要なピースとして、複雑な思いとともに今も見つめています。
海外か、それとも凡庸な人生か
人生の重要な条件分岐点において、自分が何を思い、何を決めたか、未だにその場面の記憶が鮮烈によみがえる。ぼんやりと国連で働くことを考えて大学に入学した私は、早期に国際関係を専門とする教授*1 を訪ね、必要な経験や勉強などについて質問した。「修士以上の学歴が必要」と告げられた私は、経済的な理由を背景に、早々にその道を諦める。今の私のような大人から見れば、「本当に諦めたくない夢ならば死ぬ気でバイトでもしてお金を溜め、自費で院進学すればよかっただろう」と、小賢しく言える。しかし、当時の私にそんな柔軟な考えは持てなかった。
令和の時代に入り、大学生の半数以上が奨学金を受給しているとのデータがある*2。当時、奨学金受給のために定期的に書類を大学で書いて提出していたが、〆切間際に私と同じような学生が必死な顔をして書類を書いていた場面を思い出す。その中に、髪を染めてチャラチャラした印象の地方出身クラスメイトも見かけた。後に痛感する「人を見た目で判断してはならない」という原則にも通じるが、私は意外な気持ちでいそいそと書類を仕上げた。
大学入学時、両親は60歳。年の離れた兄二人は色々とあって非正規の仕事をしていた(今では、正規雇用で働いている)。母親も自営で働いていたとはいえ、父親は家のローンも教育ローンも抱え、普通であれば子ども3人を県外はおろか、大学に行かせる余裕などなかったことは前にも述べた。兄がバイト代から私の生活費を支援してくれている状況で、私は卒業と同時に500万円の借金を抱えて社会に出ることを考えると、どうなるかもわからない大学院の2年間は鉛のように重く感じられた。加えて、学費の免除申請も行うレベルの学生が、もはや次の学歴を望むべくもないことは明らかだった。そして、金銭面の心配とはかなり矛盾するが、私は大学生活を充実させるため、オーケストラ部に所属してそれなりのエネルギーを注いでいたのも原因だった。これがまた、お金のかかる部活動だったのだ。
ある日、学費の免除がかなわないことがわかり、実家から「学費が払えない」と連絡を受けたことがある。私は迷うことなく、海外への旅に行く用途で貯めていたお金で学費をまかなった。実家に帰って、恐らく一生で一度の家族会議だったと記憶しているが、家族が悲痛な面持ちで私に詫び、めったに感情を見せない二番目の兄が泣きながら話し、父親の涙を初めて見たこともよく覚えている。もちろん、私にとっては悔しい経験だったが、あっさりと次を考えて前を見る性格が幸いしたのか(私の唯一の美点と思われる)、とにかく大学生活を楽しむことに目を向け続けた。卒業前には、オーケストラ部の仲間たちとドイツへの演奏旅行を果たし、思い残すことは何もなかった*3 。
大学一年生の早い時期に将来キャリアの一つを諦めた私は、海外を舞台に働く別の道を模索し始めた。とはいえ、二十歳そこそこのぼんやりとした男子学生の考えなど浅いもので、何となく民間で働けばいいかとかその程度のものだったし、大学生活に慣れるのにも精いっぱいだった。しかし、「いつか海外に行かねば。そうでなければつまらない人生が待っているだけだ」と意味のわからない使命感の火は消えることなく、その後に海外で仕事をする機会にも恵まれたものの、学生時代から20年を経た今でも私の胸の中に残っている。
*1 この先生は、2025年3月、日本人として2人目の国際司法裁判所(ICJ)所長に選出された https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z0101_00105.html
*2 公益財団法人 生命保険文化センターウェブサイト https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/761.html 日本学生支援機構「令和4年度 学生生活調査」より
*3 以下に続く部活動の文章も併せると、私はとても充実した(いわゆるリア充の)大学生活を送っていたように見えるが、高校来の親友富永氏(大学同窓、現財務省勤務)や小学校来の友達とだらだらと遊ぶ時間も多くあり、ゲームやインターネットにはまり、堕落的で、どこか退廃的な香りのする学生生活も送っていた
音楽は人生の糧
大学に入ってみて、「お金持ちの家が多いんだな」と最初に思った。子どもの時は「たくさんゲームを買ってもらえる家とそうでない家」くらいの認識だったが、大学生で感じたものは明らかな「格差」だった。身なりもそうだが、お金の使い方の感覚が地方の田舎者とはまったく違った。現在でも以前と状況は変わらないようだが、東大生のいる家庭の世帯年収は750万円未満が全体の25%以下で、1050万円以上になると40%以上となっている*4 。特にお金のことで卑屈になった記憶はないが、世界を知る良い機会になったと思う。実際、性格的に屈託のない人が多かったし、嫌な感じのする人はほとんどいない。いたとしても、それは若さゆえか、家庭環境の影響だったのだろうと思う。逆に、私の方が浮いていたかもしれない。地方出身者(かつ、低所得)が経験する得も言われぬカルチャーショックは、ほとんど一様に、最初の頃に訪れる。
いずれにせよ、大学一年生の春に、私は入学前から考えていたオーケストラ部(東京大学音楽部管弦楽団、通称:東大オケ)に入部した。高校の吹奏楽部で始めたファゴットという楽器を、オーケストラでもやってみたかったからだ*5 。吹奏楽部の顧問の先生に「ファゴットは本来ソロ楽器だから」と教わり、自分のお小遣いで福岡にやってきたベルリン放送交響楽団(確か、チケットはB席8,000円くらい、ショスタコーヴィチ交響曲第5番のプログラム)を聴きに行き、プロの演奏にとても感銘を受けた。部活の先輩が東大のオーケストラ部に入っていて、高校に遊びに来た際に「N響(NHK交響楽団)の先生に教えてもらえるくらいすごい」と聞いて、もしチャンスがあるならなぁ、くらいに思っていた。
お金の心配は大いにあったが、オリエンテーションで先輩の説明を聞き、バイトもすれば何とかなりそうだとどんぶり勘定で入部した。良くも悪くも、ここでの経験が無ければ私の人生はまた別のものになっていたと確信している。音楽は、間違いなく私が人らしく生きるための糧となった。得るものが大きかった分、失ったものも数多くあったが。
ここで、4年間のオーケストラ部生活について書き記そうとすると、一冊の本を書けるくらいの話になってしまう。したがって、私が仕事に臨む上で影響を与えたいくつかの重要要素に絞って、ごく簡潔に書き記す。時代感とは無関係だが、組織づくりに臨む私の価値観を理解する手助けにはなるはずだ。
全ては「基礎・基本」の上に成り立つ
普通に考えれば信じがたいと思うが、演奏会本番終了後を除いて、私は大学生活においてほとんど毎日楽器の練習にいそしんでいた。さらに、「基礎練習」を欠かすことはなかった。「凡事徹底」の言葉どおり、愚直に同じことを繰り返す。ただし、機械的に行うのではなく、目的的に取り組むことが重要だった(目的性訓練の反復)。したがって、仕事においても、目的を意識しながら、「基本」とは何か、確立すべき「基礎」は何なのか、そこを軽視せずに積み重ねてきたことが今の私を支えているし、「基礎・基本」を重視する姿勢はずっと貫くだろう。
プロに教わることは、自らを客観視して前進すること
音大生でもないのにひたすら訓練を積んだ私は、それなりに腕を上げたのか、大学4年目を迎える頃にプロの先生方にほめられるくらいにはなっていた(社交辞令のようなものもあったとは思う)。しかし、これは才能やセンスなどではなく、基礎の上に、さらにプロの教えがあってこそと言える。技術の上達の過程では、なぜか上手く行かず、何をやっても改善せずに一人ではまりこんでしまうことがよくある。プロの目から見ると、私の悪いクセや無意識の姿勢が原因と瞬時に見抜かれ、たちまち解決してしまう。そういう経験が何度もあって、その道のプロから教わることが非常に重要であると私は強く学んだ。私は、自分だけでは解決できないことがたくさんあることを知っているし、わからないことは必ず人に聞く。組織に、積極的に他者から学ぶ機会や、教え合う文化を根付かせようとしているのは、このような経験にもとづいている。
垣根を越える
総勢130名程度の集団活動において、全員と等しく同じような関係性を持つことは不可能だろう。どうしても偏りが出てしまうし、タテ(グループ)・ヨコ(学年)の線が無意識に引かれてしまう。組織の縦割りのようなものだ。私の場合、どうやらその境界線が見えないのか、見えないふりをしているのか、無自覚にその線を越えてコミュニケーションを取ることが多かった。後年、それは私のひとつの強みだと気付くことになるが、半面、私の軽率さが人を傷つけることになったのも強く反省することにもなる。私のつくった会社では「マルチプロフェッショナルたれ」と言うことがよくある。マルチな知識、マルチスキル、マルチタスク、マルチコミュニケーションを前提として求めているのは、私の生来的な部分に根差しているのだろう。それが有益だからとかそういうことではなく、ただ、面白いかどうかだと思う(飽き性なのもきっと影響している)。
機会提供と組織的訓練サイクル
オーケストラ部では幼少の頃から楽器を習っている人も多く、音大生と言っても遜色ないほどの腕前の人がいて、その上手さには惚れ惚れするレベルだった。一方で、初心者の人も多くいた。私は「一日練習は2時間まで」と決めていたが、彼らの中にはいつ講義を受けているのか、朝に練習場所にいたと思ったら夜も顔を見て、その生活ぶりが謎に包まれている人も少なからずいた。彼らの練習熱心ぶりは私などとうに霞んでしまうほどで、その上達ぶりに彼らから刺激を受けることも多くあった(結果として、初心者に限らず、練習に命をかけ、単位を落とすなどして留年する人も多かった。私は奨学金のこともあったので、順当に単位を獲得していたが、法学部生では珍しい方だったかもしれない)。
なぜ彼らがそこまでして練習に臨んだかといえば、「全員に本番演奏の機会が与えられていた」ことが大きいと思う。もちろん、突き詰めるタイプの人が多く、楽器の面白さや協奏の素晴らしさへの情熱があったのもあるだろうが、本番のプレッシャーもあった。後で知ったことだが、他大学ではお金で助っ人を呼んできたり、必ずしも部員が本番に乗れないことがあったりするらしく、機会提供の側面から思想が異なるものだと思った。初心者か否か、楽器が上手いかそうでないかに限らず、等しく機会を設けてそれを目標に向かうことは、組織として一体感を持たせるし、余計な調整や考えを減らせるメリットの方が組織的には大きいと感じる。ただし、品質(演奏の質)への影響があるのは事実で、それがあつれきを生むこともしばしばだったが、そもそも私たちはプロではなかった。大切なのは取り組みの姿勢と、練習プロセスなのだ。
私が感心したのは、個人に合わせた技能向上の仕組みが備わっていたことだ。個人の練習努力では限界があるため、弦楽器では必ずメンターがつき、今でいう1 on 1の練習を定期的に実施する。その上に、自主的なグループ練習(そこでは誰かがリーダーシップとファシリテーションを担わなければならない)、プロの先生によるグループ練習、そして、プロ指揮者による全体練習が、計画的に、サイクルとして用意されている。本番までを含めた組織的なプロセスが、極めて実効的な機械装置のようでもあり、様式美そのものだった。特に中小企業では、従業員の能力・技能向上の設計すらなされていないことがほとんどであるし、そもそも熟練や発達に対する育成思想がないことも多い。ここでも人の可能性をどう見ているか、本質的な人間観が組織のあり方を左右しているように思う。
音楽と、生涯の仲間と、喪失と
私は社会人になってしばらくしてから、音楽活動に再度参加するようになった。そこでまた運命的な出会いに遭遇することになるがそれはさておき、私が大人になってから音楽について考えたことや学んだことについて、外部のブログにまとめている*6 。子どもが生まれてから、もう楽器を触ることはなくなったし、今後も触ることはないだろうと思うが、ただ勉強だけをしていたとしたら、やはり私は全く違った人間になっていただろう。音楽を通じて出会えた一生の仲間たちとの付き合いは、昔も今も私を本当に励ましてきてくれたし、彼・彼女たちと出会えていなかったら、とてもつまらない人生になっていたと確信している。しかし、それも遡れば実家にピアノがあり、お金の無い中でも私にピアノを習わせてくれたのが遠因としてある以上、やはりそこは環境への感謝しかない。
出会いから20年が経ちオーケストラ部の仲間たちが幸福そうな人生をそれぞれ歩んでいることは、筆舌に尽くしがたい感慨を私に抱かせる。様々な事情から(私が原因を作ったものもある)、関係が切れてしまった人がいるのは悲しいことではある。しかし、生きてさえいればまた出会うことや風の便りを聞くこともあるだろうと思い、それは心の支えにもなる。何の宿業を背負ったのか、避けがたい運命の糸を手繰られてしまったのか、若くして命を失ってしまった存在、そして、私の心の一部は永遠に欠けてしまったのだと同時に語りかけてくる記憶こそ、救いようのない悲哀である。
人間関係がもたらす豊かさと、掛け替えのない大切な価値(そして、私自身の数多くの失敗)を教えてくれた部活動には感謝しかないが、いつまでもその宝石のような時間を過ごすことはかなわない。社会という現実の、極めて実際的な海へと私は旅立たなければならなかったのだ。
(続く)
*4 東京大学 2023年度(第72回)学生生活実態調査結果報告書 https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400258139.pdf
*5 「ファゴット」という名前を聞いてわかる人は20~30名くらいに1名くらい(個人統計) YAMAHA 楽器解体全書 https://www.yamaha.com/ja/musical_instrument_guide/bassoon/mechanism/*6 ビジネスでアートが注目される今、クラシック音楽を僕は再考する https://note.com/harryike/n/n6210f53d6cd9